今月の一冊
「アフターダーク」
村上春樹
|
>>>>> |
 |
 ブックレビューをご覧の皆様、夜更かしの好きな浅羽です。 ブックレビューをご覧の皆様、夜更かしの好きな浅羽です。
ある人が夜明け前の新宿の名もない店で、小説家にはふた通りあるのだと言っていた。外側の情報を異常な好奇心で拾い集めて小説世界を構築する人と、内側に流れ込む情報を異常な感受性で堰き止めて物語を紡ぐ人。あなたが小説を書くとしたら、どちらのタイプですか?
僕のブックレビュー第1回目には、典型的な後者の小説家、村上春樹の作品を選んでみました。
内側の世界から物語を紡ぐタイプの小説家は、1人称小説がお得意。「私」というフィルターを通して世界を描き、人を描く。初期3部作にしても「ノルウェイ」にしても「ねじまき鳥」にしても、主人公「僕」の物語を、語り手である「僕」が綴っています。
内側に構築された似たような世界観で、似たような1人称小説を書き続けてきた村上春樹ですが、この作品では文章的に面白い試みをしています。
「アフターダーク」にはお得意の「僕」が作中人物として登場しないのです。これは春樹的には大革命ですね。編集者にゴリ押しされたのか、単なる気まぐれか、3人称小説を書いてやろうじゃないの! ってのが前提としてあったように思えます。
しかし3人称小説の体裁をとりながら、1ページ目から早くも「私」が登場している。このあたり永年の習性は恐ろしいというか、面白いですね。
3人称小説においては、語り手は人格を与えられることのない視点に過ぎません。情景を描写し、登場人物の心情を描写して、読者に情報を提供するただの視点。
村上春樹はこの視点を「私たちの視点」にしてしまい、語り手に人格を与えました。私たちというのは、語り手と読者ですね。
「私たちの視点は架空のカメラとして、部屋の中にあるそのような事物を、ひとつひとつ拾い上げ、時間をかけて丹念に映し出していく。私たちは目に見えない無名の侵入者である。私たちは見る。耳を澄ませる。においを嗅ぐ。しかし物理的にはその場所に存在しないし、痕跡を残すこともない」
そんな風に「私」が語る奇妙な3人称小説は、まるで小説教室のごとく語り手の役割について講義しています。
講義といっても別に堅苦しくもなく、こんな風に物語の中で読者であることを意識させられるのは、不思議な感覚に浸れるものです。何より事象を描写する作業が多いので、これまでの村上春樹作品よりも凝っている感じで読み応えがあります。
さて、文章的には面白い試みに挑戦しているのですが、構成は村上春樹ワールドそのもので、彼独特の世界観が見られます。
ひとつの時間に複数の現実、ひとつの場所に複数の次元、それらを非現実的な手段も含めて相関させるアイデアは、過去の村上作品にもいくつか登場しました。
小説のアイデアにも特許があるのか、田口ランディが初期の作品で春樹の小説に出てくるアイデアや言葉を模倣しているのですが、そういうのを見ると、ああくだらないって感じてしまいます。でも、春樹が過去の春樹作品のアイデアを使いまわしてもなんだか許せる気がします。それどころか、待ってましたと「水戸黄門的快楽」すら感じてしまう。
音楽に関しても相変わらずで、その道に精通している人しかわからないようなマイナーな単語を連発し、果たして場面に相応しいのかどうかさえわからない。でも知っている人には「待ってましたの快楽」をもたらすことでしょう。
単語といえば、冒頭の街の描写はひとつひとつの単語が古臭いというか、都会の猥雑さとそこに漲るエネルギーを表現するには、あまりにも陳腐な単語を選んでしまっています。このあたり、村上春樹も歳を取ったのだなあと思わせます。
冒頭に大きな謎を読者に提供し、その謎の核心に向かって物語が進み、最後に全てが明かされるという典型的なミステリー小説を引き合いに出して比べると、この作品も謎が読者を次のページへ引っ張っていきますが、さすがに純文学作品は無責任です。
夜から朝までの間にいくつかの場所で何人かの人々が起こす出来事が相関し、それを「私」という語り手が読者に話して聞かせるという物語なのですが、数ある謎のうちはっきり解決されたものはひとつもない。
夜の闇の中に蠢いていた意図や思考も曖昧なまま、太陽が全てを照らして朝を迎えると、その光の中に消え入ってしまう。微かな方向性だけが示され、それを読み取るのが作品の機微を味わう快楽になる。ですが、それを語り手「私」が読者に語ってしまっているところは、ちょっとあんた黙っててよと言いたくなります。
眠って意識が無くなってから、起きて意識が生まれるまでの間に世の中で起こっていることについて僕らは何ひとつ体験できません。だからって眠らない訳にはいかない。
人々の多くは夜眠り、朝起きます。「夜と朝の間」というテーマはそんな非日常ゆえの魅力があり、これまでもジャンルを問わず様々な作品が生み出されています。
終電が無くなると、街は少なくとも夜が明けるまで孤島となる。軒を連ねる深夜営業の小さな店の中、語り疲れてただ始発を待つ感触って不健康で怠惰なのだけど、それを否定して早寝早起きをするのって無粋な感じがします。
街に留まる無縁な人たちはそんな感覚を共有しているように思う。だから関わると簡単に融合するのだけど、ある距離を守る必要がある。その距離が崩れたとき、物語が進展し、無責任な可能性が生まれていく。
しかし、それも夜が明けてしまえば、朝の太陽の作用によって儚くも全てリセットされてしまう。そこにあった無責任な可能性も消え、微かな方向性が残骸として示されている。
作品を読み終え、やはり「待ってました」の春樹作品に違いないが、ねっとりとした男女の描写が今回は無かったことに気付いた。
本を閉じて窓の外を眺めると、夜は終わりに近づき、生白い空が闇を凌駕しようとしていた。けたたましく鳥が鳴き、やがて来る始まりの朝を呼んでいた。
| 評者→浅羽 祐治(33歳):小説との出会いは19歳の頃でした。喫茶店が好きで、隅っこの席に長時間居座っ
て、片肘ついてアンニュイに煙草をふかし、手垢のついた文庫本に没頭する学生、と いうポーズをしてみたかったから。 |
バックナンバー
| 
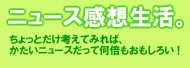



 ブックレビューをご覧の皆様、夜更かしの好きな浅羽です。
ブックレビューをご覧の皆様、夜更かしの好きな浅羽です。