今月の一冊
「聖者は海へ還る」
山田宗樹
|
>>>>> |
 |
 ブックレビューをご覧の皆様、阪神優勝の気配に心踊る浅羽です。 ブックレビューをご覧の皆様、阪神優勝の気配に心踊る浅羽です。
数年前、放射能研究所に勤めている知人と「創作家が作り出す世界のディテール」について話をしたことがあって、彼女が言うには、真実らしさを与えるために科学的な仕組みや単位を使うことで、却って失敗してしまう作品をよく見かけるとのこと。
その数値、その単位では液体として存在しているはずのないものが、作品中では液体として使われていたり、人の目に見えるはずのないものが色付きで描かれていたり。
固有名詞や数字は「真実らしさ」を与える武器ですが、よく理解して使わないと大変な恥になってしまう。一般人にはわからなくても専門家はその分野を熟知していて、作品は読者を選ぶことなく公開されてしまいます。
真実らしさを与えたいのに、「ここだけの真実」になってしまっては身も蓋もない。
だからって実体験に基づくことしか書けないのでは、小説家は務まりませんよね。想像力と探究心が実体験を上回って作品が生まれる。山田宗樹の作品にはそんな想像と探求の過程を感じます。
ベストセラーとなった「嫌われ松子の一生」では、主に風俗と犯罪の世界に生きる人々を描いている。「天使の代理人」では産婦人科、出産中絶に関わる人々、そして「聖者は海に還る」では、精神医療と進学校という分野。
これらの全てに専門家並みの実体験を得るなんてできないので、想像力と探究心で補うわけですが、巻末の膨大な参考文献がその探究心の深さを物語っています。山田宗樹自身がそれを大変な苦労と考えているか、この程度の努力で済むなら容易いことと考えているかはわかりませんが、まさに研究と言っても過言ではない。
さて、山田宗樹の作品は複数の話者に出来事を語らせるという手法を用いています。これは現在の彼の作風とも言えます。
時間的、距離的に無関係なふたりの話者がそれぞれ物語を進めていきます、最終的にはそのふたりが関係しクライマックスへ向かう。
まったく無関係のふたりが違う話をしていても、読者にはきっとこのふたりの物語が結びついてくるに違いないということは簡単に想像できます。そこで、ではどんな風に結びついていくのだろうという謎が読者の関心を深めます。
この手法って、読者を惹きつける謎を作る方法としては、簡単だし結構いろんな人が使っています。3回やればもう「お替り」はいいんじゃないでしょうか。
某小説家が、5年に一度は新しい作風に挑戦し、5作に一度は渾身の一作を書き上げなければ小説家とは言えないなんて言っていたが、山田宗樹も次の作品は勝負ですね。今の作風で売れているから、編集者や読者が革新を許すかどうかは疑問ですが。
山田宗樹の作品で最も素晴らしいと思うのは結末の部分です。
不幸な主人公が次々と不幸な境遇に追いやられ、不幸の累乗で物語を盛り上げ、最後に大逆転のハッピーエンド、というのはハリウッド映画によくあるフィクションです。これに対して数年前から救いのない結末というのが流行っていて、不幸の累乗で物語を盛り上げ、そのまま突っ走って終わるというフィクション。主人公が死んで終わり、一切救わないという結末。
山田宗樹の作品はどちらかというと地味で、ハッピーとは逆の物語です。特に「嫌われ松子」は不幸の累乗が見事に表現されています。でも、彼は大逆転のハッピーエンドにもしないし、一切の救いなく物語を終わらせることもしない。
この匙加減ってものすごく難しいと思うんですよね。救いすぎたらお笑い作品だし、救いがないのも食傷気味。この辺りが「嫌われ松子」にしても「聖者は海へ還る」にしても絶妙なんですよね。得も言われぬ読後感に浸れます。
ふたつの物語がひとつに重なった瞬間の快感、幸福な場面を信じない自分に未来の快感を予想し、累加された悲劇に快感を覚える。大逆転もなく、残虐でもない終末がじわりじわりと胸の奥底に広がっていく。
今朝も夜明け前の寝室で、得も言われぬ読後感に浸りながら美味しい珈琲を啜り、裏表紙を撫でて「お見事」と呟くのでした。
| 評者→浅羽 祐治(33歳):小説との出会いは19歳の頃でした。喫茶店が好きで、隅っこの席に長時間居座っ
て、片肘ついてアンニュイに煙草をふかし、手垢のついた文庫本に没頭する学生、と いうポーズをしてみたかったから。 |
バックナンバー
| 
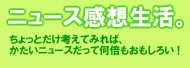



 ブックレビューをご覧の皆様、阪神優勝の気配に心踊る浅羽です。
ブックレビューをご覧の皆様、阪神優勝の気配に心踊る浅羽です。