 |
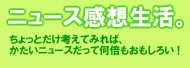 |
 |
| 音楽レビ ブックレビ ひとこま画像 | 2003年3月5日号 | |
 |
| 【隔週更新映画レビュー】 著:システム開発会社勤務 青木泰子(30) |
監督は巨匠ロマン・ポランスキー。ポーランド人の両親を持ち、彼自身ゲットー(ユダヤ人居住区域)の生存者でもあります。にもかかわらず「現実をできる限り忠実に描いた」と語るように、彼は悲劇の連続をひたすら淡々と撮っています。主演には『シン・レッド・ライン』などで知られるエイドリアン・ブロディ。とても個性的で、一度見たら忘れられない俳優です。今回、彼の悲しみにあふれた表情は、実にハマっていました。この作品は彼の代表作となるでしょう。 『シンドラーのリスト』などの今までのホロコースト映画は、ホロコースト(大虐殺)の悲劇を前提に描かれていると思うんです。つまり、現代人が過去を振り返るという客観的な視点がどこかに存在していた。しかし今作は、徹底して当時のユダヤ人の視点で描かれています。財産・所持金の没収に始まり、ダヴィデの星(ユダヤ教の象徴)の付いた腕章の着用義務、舗道歩行の禁止、ゲットーへの移住、最終的には絶滅収容所への移送と、ユダヤ人が迫害されていく過程をこれでもかというほど綿密に時間をかけて描いている。 私たちは史実として選民思想やホロコースト、ガス室などの存在を知っていますが、当時の人々には、ヒトラーのもくろみが全ユダヤ人抹殺計画であるなど知る由もなかった。第二次世界大戦という言葉すらなかったのです。そんな当たり前のことに、ハッと気づかされます。 「近いうち戦争は終わる」という漠然とした希望。その希望を頼りに無抵抗に生きる日々。しかし彼らの生活は確実に制限されていく。そして、理由も無く唐突に行われる虐殺。小さくなっていく希望。次々と理不尽な死を与えられる人々。次第に麻痺していく死への恐怖。まるで予防接種を受ける小学生のように、並んで自分が処刑される順番を待つ。当時のユダヤ人の視点で、この過程をここまで丁寧に描いた作品は、初めてではないでしょうか。 戦争において善悪を語ることは危険だ。今、アメリカのイラク攻撃が近づいている。アメリカはどうしても戦争をしたいようだ。ならば、アメリカが悪なのか?査察を受け入れているイラクが善なのか?いや、反戦を説くフランスですら善とは言えない。結局それぞれが自分の利益を考えて行動しているだけだ。そこには明確な善悪など無い。 「ポーランド人にも悪人はいたし、ナチスの中にも善人はいた」とポランスキーは語る。しかし、ナチスがポーランドの人々にした行為は悪そのものだ。引き金を引く指一本で、蚊を殺すよりも容易に、そして無感情に殺しまくるゲシュタポ(国家秘密警察)。女だろうが、子供だろうが、老人だろうが1ミリの躊躇もない。そしてほとんど無抵抗に死にゆく人々。ナチスの行為は正に人間に対する冒涜である。これを悪と言わずして何が悪なのか! この作品には、ピアニストものによくある爽やかな感動などほとんどありません。そんなものなくて当然です。現代史において最も忌むべき出来事をありのまま描こうとしているのですから。
|

 「映画は娯楽である」と思うのです。観客を泣かせようが、悲しませようが、それは娯楽の範囲内でのことだ。そう思っていたのです。しかしこの映画を観て、一概にそうとは言えないということを痛感しました。第55回カンヌ国際映画祭でパルムドール賞を受賞した本作には、娯楽の範疇には収まらない、痛烈なメッセージが込められています。
「映画は娯楽である」と思うのです。観客を泣かせようが、悲しませようが、それは娯楽の範囲内でのことだ。そう思っていたのです。しかしこの映画を観て、一概にそうとは言えないということを痛感しました。第55回カンヌ国際映画祭でパルムドール賞を受賞した本作には、娯楽の範疇には収まらない、痛烈なメッセージが込められています。