 |
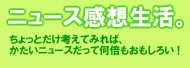 |
 |
| 音楽レビ ブックレビ ひとこま画像 | 2004年4月28日号 | |
 |
| 【隔週更新映画レビュー】 著:システム開発会社勤務 青木泰子(31) |
女性作家スザンナ・ムーアの小説を女性監督ジェーン・カンピオンが映画化。製作は女性プロデューサーのローリー・パーカーとニコール・キッドマン。製作陣が女、女、女だらけです。もともとニコール・キッドマン主演を想定して脚本が書かれたようですが、彼女は出演を断わったようです。ニコールが蹴り飛ばしたこの役を、自ら熱望したのがメグ・ライアン。最近売れてるニコールと、最近売れてないメグの差でしょうか。ともあれ、この作品に携わる主要メンバー全員が女性なわけで、「女性が創った映画」という看板に偽りなし。この作品が放つ強烈な“男は観に来るなオーラ”はここから発せられているわけです。 フラニー(メグ・ライアン)は大学の文学講師。詩や言葉を収集するのが好きな知的な女性で、他人との付き合いを極力避ける内気な性格。そんな彼女も奔放な妹のポーリーン(ジェニファー・ジェイソン・リー)にだけは心を許している。ある日、フラニーの住むアパートの庭で女性のバラバラ死体の一部が発見され、ひとりの刑事(マーク・ラファロ)が聞き込みに訪れる。何故か彼はしきりにフラニーを誘おうするが、彼の手首には彼女が目撃した犯人と思しき人物と全く同じタトゥーがあるのだった。この刑事に危険な匂い(体臭じゃないぞ)を感じつつも、今まで味わったことのない快楽に身を委ね、彼との愛欲に溺れていくフラニー。危険と分かっていても、彼女の熟れた肉体は自然と彼を求めてしまうのだった(わたしゃエロ小説家か?)。 なんだか書いてて恥ずかしくなってきたので、ストーリーはこれぐらいで勘弁してね。このあらすじだけ読めば、ごく普通のエロティック・サスペンスなのです。主演シャロン・ストーン、監督ポール・バーホーベンといった感じ。でも本作の監督は『ピアノ・レッスン』のジェーン・カンピオンなのです。「女性であることの喜びと悲しみ」をテーマに撮り続けてきた監督ならではの演出がなされているはず。と見せかけて、実はこの作品、驚くほど普通のエロサスペンスなのです。唯一、詩的な言葉と美しい映像のみがカンピオン作品っぽかった。 はっきり言って、カンピオン監督の売りであるはずの女性ならではの繊細さがこの作品には欠如しています。私は女性読者に問いたい。 恐らく、最近スランプ気味のカンピオン監督は、苦し紛れに娯楽要素の強いサスペンスものに手を出したのでしょう。片や女優メグ・ライアンは、ラブ・コメ女優からの脱却を図るため、人間ドラマを得意とするカンピオン作品への出演を望んだのでしょう。この両者の意向が見事なぐらい噛み合っていないのです。結果、カンピオン作品らしからぬ中途半端なエロサスペンスで、メグ・ライアンが意を決して脱ぎまくるという、観る側も反応に困っちゃう作品になってます。 可哀相なのは、あんな事やこんな事までして頑張ったメグちゃん。わざわざ「世界中の女性から支持される女性監督」の作品を選び、「あくまでリアルな女性を演じるために脱ぐ」という大義名分をゲットしたはずなのに、女性が全く共感できないキャラクターを演じてしまった。女優としてのステップアップ大作戦、ちょっと失敗。悩める女優メグ・ライアンの明日はどっちだ?
|

 ラブコメの女王メグ・ライアンがその女優人生を賭けて「全てを脱ぎ捨てた」という本作は、男ひとりで、もしくは男同士で観に行くのがとーっても恥ずかしい映画です。それは本作が自称「女性のための官能映画」だから。レディース・デーに観に行ったせいもあってか、客席は女、女、女だらけ。年齢層は若い女の子からおばちゃんまで、結構幅広い。まるで銭湯の女湯のようです。ムンムンしてます。私も女の端くれとしてその中に混じり、メグの女優としての成長ぶり(主に脱ぎっぷり)をチェックしてきました。
ラブコメの女王メグ・ライアンがその女優人生を賭けて「全てを脱ぎ捨てた」という本作は、男ひとりで、もしくは男同士で観に行くのがとーっても恥ずかしい映画です。それは本作が自称「女性のための官能映画」だから。レディース・デーに観に行ったせいもあってか、客席は女、女、女だらけ。年齢層は若い女の子からおばちゃんまで、結構幅広い。まるで銭湯の女湯のようです。ムンムンしてます。私も女の端くれとしてその中に混じり、メグの女優としての成長ぶり(主に脱ぎっぷり)をチェックしてきました。